 マイ催事記
マイ催事記 初午ってなに?初午の「意味や由来」、いなり寿司を食べる理由は?
初午とは初午(はつうま)とは、2月の最初の「午(うま))の日」を指します。稲荷神(いなりしん)のお祭りが行われる日です。稲がなることを意味する「いなり」から、五穀豊穣や商売繁盛、家内安全を祈願して各地の稲荷神社でお祭りが行われてきました。稲...
 マイ催事記
マイ催事記 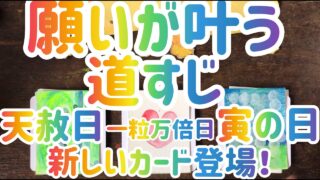 マイ催事記
マイ催事記  マイ催事記
マイ催事記  マイ催事記
マイ催事記  マイ催事記
マイ催事記  マイ催事記
マイ催事記  マイ催事記
マイ催事記  マイ催事記
マイ催事記  マイ催事記
マイ催事記  マイ催事記
マイ催事記