一休さんは、室町時代の有名な禅僧です。
室町時代は、足利尊氏が建武式目を制定した1336年から15代将軍義昭が織田信長によって京都から追放される1573年までの237年を指します。
一休さんは、3代将軍義満の時代から8代将軍義政の時代に生きた禅宗のお坊さんです。
義満は、1397年(応永4)、一休さんがまだ4歳のころ、衣笠山のふもとの北山に金閣(鹿苑寺)を建て、ここを中心として古い公家の文化と新しい武家の文化を調和させようとしました。
また、義政が東山山荘(後の慈照寺銀閣)を建てたのは、1482年(文明14)であり、一休さんが亡くなった翌年のことです。


一休さんは華やかな北山文化(金閣寺)と、簡素な東山文化(銀閣寺)とのちょうど間の時代に生きた!
義満は、1392年(明徳3)南北朝統一の最初の天皇として、後小松天皇の即位を見ました。そして、この2年後に一休さんは生まれました。
一休さんは、後小松天皇の子供だと伝えられていま。一休さんの墓のある山城の国、薪村(京都府綴喜郡田辺町大字薪)の酬恩庵(一休寺)には、「後小松天皇皇子宗純王墓」の立て札があります。

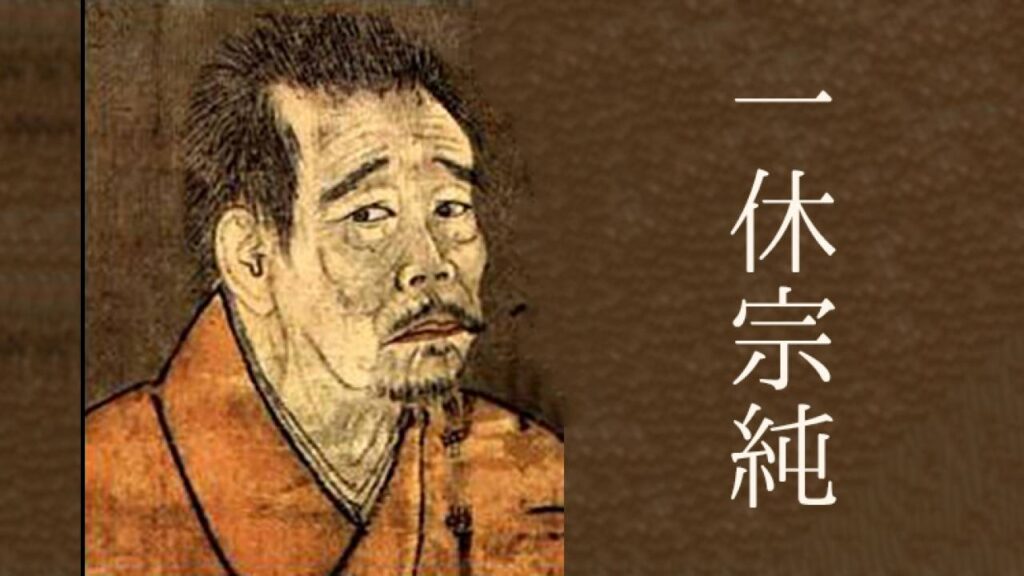

南北朝時代から室町時代を経て戦国時代にかけて、社会は大きく変動、「下剋上」へ
「下剋上」とは、身分の下の者が上の者を押しのけて、勢力や権力を握るという意味です。
南北朝は合体したものの、朝廷や貴族は実力を失い、室町幕府さえも、地方の武士たちを強く取り締まる力を持ちませんでした。
一休さんは「この世は地獄」だと考え、人間はどのように生きるのかを説いて、社会のあらゆる人々から親しまれ尊敬されました。
一休さんは、自分のかわいがっていた雀が死んだとき、ひどく悲しんで手厚く葬り、お墓を建て、弔いの言葉をつづるというように、すべて生き物の命を大切にする、情け深いお坊さんでした。
天皇の子として生まれ、いつも質素で人々の幸せを願って生きた。いたずら好きで、変り者和尚と言われた。自然を愛し、人の心の善を信じて生きた名僧
とんち小僧の一休さん、その数々のとんち話は、笑いの中に、ちょっぴり苦い味があります。
金閣寺、銀閣寺が建った華やかな室町文化の裏側には、戦乱、飢饉、悪病の流行、洪水、台風、地震、津波、大火など様々な災いが相次ぎ、世の中は不安におののいていました。
一休さんが、よれよれの衣をまとい、擦り切れた草履を引きづり、竹竿の先にどくろを刺し貫いて、「この通り、御用心、御用心・・・」と叫びながら、正月の家々を回ったのはどうしてでしょうか?ここに、一休さんの本当の心、本当の姿があります。
「偽坊主」「気違い坊主」と皆から嘲られても真実一路、自分の信じる道を生き抜いた一休さん。
とんち話と、童話だけの一休さんでなく、もう一人の一休さん。
一休さんは今も生きています。
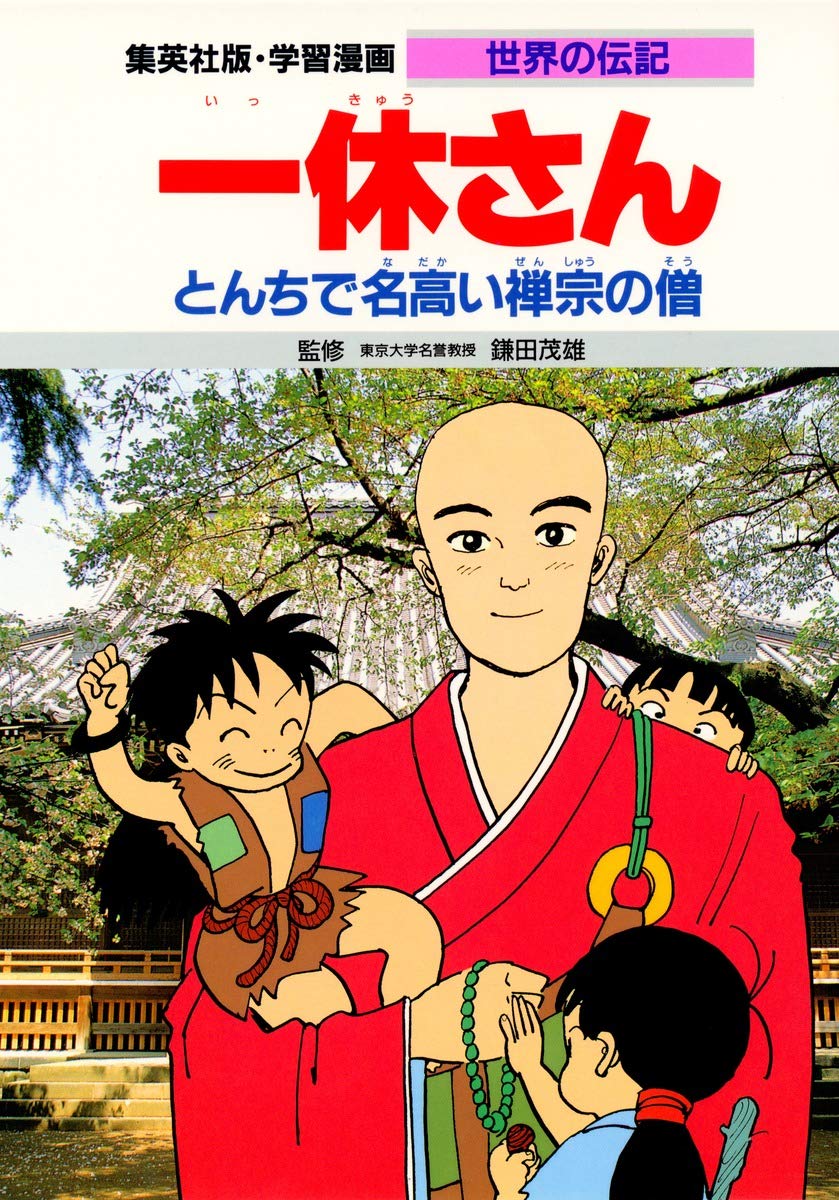


コメント