梅が満開と聞いて、2月末日に向島百花園に行って来ました。初めて行った歴史のある場所なので、ここにまとめて記録を残したいと思います。さらに、亀戸天神にも回って、観梅に浸りました。
向島百花園は、今から200年前の文化・文政期(1804~1830年)に骨董商を営んでいた佐原鞠鵜(さはらきくう)が、花の咲く草木鑑賞用の花園として開園されました。
百花園とは、「四季百花の乱れ咲く園」という意味で名付けられました。開園当初は、360本のウメが主体でしたが、その後四季を通じて花が咲くようになりました。
昭和13年(1938)に、永久保存のため所有者から東京市に寄付され、昭和53年(1978)に文化財保護法によって国の名勝・史跡に指定されました。
文人たちの足跡
入り口付近の庭門には、蜀山人(しょくさんじん)の扁額(へんがく)が掛かっています。蜀山人は、天明期を代表する文人・狂歌師であり、御家人である大田南畝(おおたなんぽ)の別号(=別名)です。
扁額とは、建物の内外や門・鳥居などの高い位置に掲出される額・看板で、書かれている文字はその建物や寺社名が多い。
また、門柱には江戸後期の漢詩人の大窪詩仏(おおくぼしぶつ)が書いた「春夏秋冬花不断」「東西南北争来」と掲げられています。
そのほか、松尾芭蕉の句碑や、合計29の句碑や、石柱が園内随所に建っています。庭造りに力を合わせた文人墨客(ぶんじんぼっきゃく)たちの足跡を辿ることができます。
花の棚
藤(フジ)は、5月上旬頃に棚全体に花房が下がって見ごろを迎えます。
また、他では見られないミツバアケビやクズの棚もあります。ミツバアケビは、4月上旬頃に黒紫色の花をつけ、10月上旬頃に淡紫色に色づいた実も楽しめるようです。クズは8月に入ると、紫紅色の花をつけ、下旬頃から見ごろを迎えて辺りは特有の甘い香りに包まれるということです。
つる物棚
ヒョウタン、ヘチマ、ヘビウリは棚で栽培する一年生つる草ですが、7月頃開花し、8月から9月にかけて、結実して棚から下がっているそうです。
池と水辺の花
ハナショブなどが色とりどりの花を咲かせ、夏にはハンゲショウなどが楽しめます。
野鳥・昆虫
ウグイス、シジュウカラ、メジロなどの野鳥が訪れます。スズムシ、コオロギ、マツムシなどが奏でる音色も楽しめます。
ハギのトンネル 百花園の名物!
ハギを竹で編んだトンネルに沿わせて仕立てたもので、これが百花園の名物になっています。
9月下旬には、全長30メートルの花のトンネルになります。
亀戸天神 梅まつり
菅原道真公を祀る亀戸天神は、一般には広く「亀戸の天神さま」「亀戸天満宮」と呼ばれ、親しまれています。
1662年(寛文2)に大宰府の杜に倣って、社殿、回廊、心字池、太鼓橋などを営み、以来約300年後の今日まで東国天満宮の宗社として崇敬されてきました。
<梅まつり>
菅原道真公は、梅の花を好まれ、多くの和歌を詠まれました。
そのため、境内には300本を越す梅が植えられ、紅白の花が咲き始め、春の息吹を感じます。

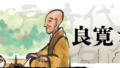

コメント