「良寛」さんは、雪深い越後(新潟県)、日本海の波が打ち寄せる出雲崎の名家の長男として生まれました。
18歳で名主見習いになった栄蔵(良寛)は、恵まれた生活を捨てて坊さんになったのはなぜでしょうか?
漢詩、歌、書を書き子供たちと「手まり」をついたり、かくれんぼをして遊びながら、やさしい心の花をいっぱい子供たちの胸に咲かせました。


「かすみたつ ながき春日に 子供らと 手まりつきつつ この日くらしつ」
<年表>
・1758年(宝暦8) 越後の国(新潟県)出雲崎の代々名主の橘屋山本家の長男として生まれる。
栄蔵と名付けられる。父は山本以南、母は秀子
・1767年(明和4) 大森試子陽の塾に通い、論語、儒学を学ぶ(10才)
・1775年(安永4) 出雲崎の名主見習いとなったが、すぐにやめる。一人静かに物思う場所を求めて、
近くの光照寺の破了和尚のもとに身を置く。(18才)
・1779年(安永8) 光照寺を訪ねた国仙和尚の弟子となって、名を「良寛」と改める。国仙和尚につい
て備中の国(岡山県)玉島の円通寺に入り、修行僧となる。(22才)
家運の衰え、世の中の乱れを嘆き、悲しみ、悩んで、ひたすら仏の修行すること10年!
・1783年(天明3) 郷里で母秀子が亡くなる。(26才)
・1790年(寛政2) 九州、四国の各地を身一つで旅して回り禅僧となる。(33才)
破れ衣に一鉢をたずさえ、雪や風に打たれ、食べ物を乞いながら諸国を行脚すること10年!
・1791年(寛政3) 国仙和尚が亡くなる。出羽の国(山形県)で大森子陽も亡くなる。二人の師を失い、
良寛はぼんやりと天を仰ぐ。(34才)
・1795年(寛政7) 父の以南が亡くなる。円通寺を去り、郷里へ帰る。(38才)
郷里に帰った良寛は、「漢詩」を作り、「歌」を詠み、「書」を書き、子供たちと「手まり」をついたり、「かくれんぼ」をしたりして遊びながら、やさしい心の芯をいっぱい、子供たちの胸に咲かせました!
「かすみたつ ながき春日に 子供らと 手まりつきつつ この日くらしつ」
・1797年(寛政9) 郷里に帰り、村人の住んでいない草庵に転々と移り住み、托鉢して回る(40才)
・1800年(寛政12) 国上山中の五合庵という草庵に定住する。(43才)
・1816年(文化13) 10数年暮らした五合庵を出て、国上山のふもとの乙子神社の草庵に移り住む(59才)
・1826年(文政9) 20数年過ごした国上山を出、島崎村の木村元右衛門という家の離れに移る(69才)
・1830年(天保1) 病に倒れ病状悪化し、寝たきりになる。(73才)
・1831年(天保2) 正月六日、申の刻(今の午後四時)息 を引き取る。(74才)
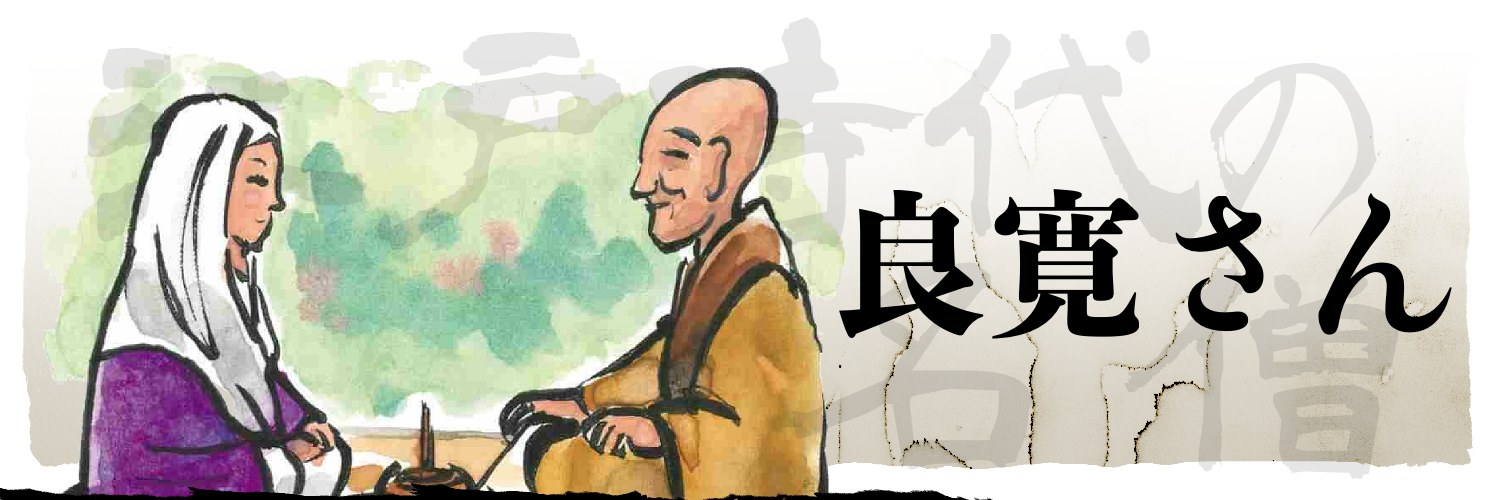


コメント